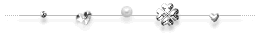
--------------氷の瞳

櫻井梓は超がつくほどの低血圧だ。
毎朝けたたましい目覚ましの音にむりやり現実の世界へ引き戻され、眠たい目をこすりながら学校へ向かう。
教室に入ると親友の辻原結衣が元気そうに挨拶して来た。
彼女は梓とは正反対に、朝から声のトーンもテンションも高い。
「機嫌最悪なとこ悪いけど、また柊(ひいらぎ)先生が呼んでたよ。行っといで」
ただでさえ悪い機嫌が更に悪化した。
しかし内申を下げられてはたまらないので、梓は仕方なく数学準備室へ向かった。
「おはよう、櫻井」
にっこりと出迎えたのは、梓の担任・柊雅也。
彼の呼び出しを食うのは一体何度目か。
非難がましい梓の視線をさらりと受け流して、
「悪いんだけど、このプリント三枚セットにしてホッチキスで止めてくんね?」
「…はい」
なぜに朝っぱらからこの男と二人で雑用をしなければならないのか。
静かな数学準備室に、プリントの擦れる音とホッチキスの針金の音だけが響いている。
ふと梓は、横からの視線を感じた。が、無視する。
すると柊は、またおなじみの言葉を言った。
「櫻井、俺と付き合う気になったか?」
「…………」
梓は呆れたように相手の顔を見た。
進級してからもう一ヶ月、これと同じやりとりが幾度となく繰り返されている。
柊(ひいらぎ)。
この男は一体何を考えているのだろう。
最初に告白されたのは始業式から一週間も経たないある日のことだった。
その時も同じように場所は数学準備室だった。
「俺と付き合わない?」
笑顔でいきなりそう告げられて、梓はうろたえるよりも先に固まってしまった。
まさか、よりによって彼にそんなことを言われるとは思ってもいなかったのだ。
「あの…」
「ん?」
「確認しますけど、あなたの職業は?」
「この高校の数学教師」
「じゃ、私は?」
「俺のクラスの生徒だな」
―――わかってるんじゃないの。
「……無理です」
この人にはモラルというものがないのか。
「何ソレ! そんな理由で断るなんて、ひどくないか?」
(……十分な理由だと思うけど……。ていうかこんな堂々と生徒に告っていいわけ、教師って。)
少々混乱しつつも、梓の頭には次に言うべき言葉だけははっきりとあった。
「とにかく無理ですから。お断りします」
梓はぺこりと頭を下げた。
もともとこの部屋にだって、資料整理のために学級委員として呼び出されただけだ。
さっさと帰ろう。
柊先生が担任になったばかりで気まずくなるのは嫌だけど、好きでもない相手(しかも先生)と付き合うなんてできない。
―――そう梓は考え、返事を待たずにすばやく扉へ向かう。
その時、柊の声が背中に飛んできた。
「櫻井」
振り向くと、彼は口の端だけを上げて笑っている。
腕を組んで余裕たっぷりに構える様子は、梓の言葉など少しも意に介していないように見えた。
「俺は諦めないからな」
「しかしアレだね、柊先生がこんなに粘るとは思わなかったよ~。
クールビューティー・梓の『氷の瞳』で睨まれたらすぐ引いちゃうと思ったんだけどなー」
「結衣、声が大きい!!」
梓はあわてて周りを見渡した。
「大丈夫だってば。昼休みに屋上になんか誰も来ないって」
先生に告白されたことを、梓は親友の辻原結衣にだけは話していた。
彼女は恋愛経験も豊富だし、何度も告白してくる柊の扱いに正直困ったので、
何かアドバイスでももらえればと思ったのだ。
が、結衣は「あんたのやりたいようにすれば?」と実になるようなならないような助言をくれただけだった。
仕方なく梓のやりたいように断り続けた結果、事態は全く進展していない。
「よっぽど梓のこと好きなんだね、先生って」
「…からかってるだけよ」
一ヶ月も悪い冗談で生徒をからかい続ける教師がいるとは梓も思えなかったが、
柊が本気だとはどうしても思えなかった。
「あの柊先生が、からかうためだけに生徒に告るとは思えないけど」
「……」
確かに柊の顔がいいのは認める。
梓は美人だが、それだけの理由で生徒に手を出すほど女には飢えていないだろう。
教え方もうまい。生徒の人望もあるみたいだ。
それでも梓は応えるつもりはなかった。
「…けど、それとこれとは別だよ。私はもう男の人とは付き合うつもりなんてないから」
だって……。
「梓、失恋を乗り切る秘訣は新しい恋だよ」
「…………」
そうかな。また傷つくだけじゃないの? 柊先生だって、「彼」と似たようなものよ。
梓は心の中でそう思った。
梓は高校一年の終わりに、付き合っていた同級生・林田修二に振られた。
「俺がいなくても平気だろ?」
別れ際、あろうことか彼はそんなことを言った。
泣いて引き止めることもできたが、何となくもう駄目だということはわかっていた。
梓は別れることを承諾した。
その数日後、林田が新しい恋人と手をつないで歩いているのを見た。
かわいらしくてニコニコしていて、梓とは正反対のタイプの女の子だった。
『クールで落ち着いてる梓が好きだよ』
そう言っていたくせに、彼は梓と全く違う性格の女と付き合い始めた。
別にクールな性格だったわけではない。
けれど彼がそう言うなら、彼からはそう見えるのならと、意識して落ち着いた振る舞いをしていた。
梓なりに彼を大切にしていたつもりだ。
なのに。
…胸がよじれそうだった。
二年になって彼と遠くクラスが離れ、ようやくほっとできたのに、今度は柊が現れた。
「…ごめん、傷つけた?」
梓は首を振った。
結衣は梓のことを心配してくれている。
それをわかっていて、彼女を責めることはできない。
「でもね梓、元彼とうまくいかなかったのは梓のせいじゃなくて、単に彼と合わなかっただけなんだよ。
一回そういう人と付き合っちゃったからって、これから先ずっと恋しないつもり?」
梓は曖昧に笑った。
(だってもう嫌なのよ。好きになったって、報われないんだもの……)
「クールビューティー」
梓は資料を整理する手を止め、後ろを振り返った。
例によってまた、放課後柊に呼び出されている。
「…って呼ばれてんだって?」
てっきり梓のほうをむいているかと思ったが、柊は梓と反対のほうを向いて、同じく資料整理にいそしんでいた。
「…一部の人はそう呼んでるみたいです。私はよく知りませんけど」
林田と付き合っていたときに形成されたキャラクターが、今でも続いている。
梓にしても、今から急にキャラを変えるわけにもいかないから、あえてそのあだ名で呼ばれても嫌がることはしない。
しかし、彼女のその落ち着いた振る舞いが、別れ話の際にはマイナスに働いた。
林田は、梓が感情を表に出さないことをイコール梓が傷ついていないと勘違いしていた。
振られて傷つかないわけがないのに。
「けど、“クール”はいいとして“ビューティー”ってのはひっかかるよなぁ。
周りの男が櫻井をそういう目で見てるかと思うと、ちょっと妬けるよ」
「…先生、本当に私のこと、本気なんですか」
「本気に決まってるだろ。まだ信じてなかったのか?」
ちょっとむっとしたような表情で振り向いた。
「じゃあ何で、私を好きになったか教えてください」
柊とはこれまでまったく接点がなかった。
高一のときの数学担当は別の教師だったし、ましてや担任ではなかった。
梓は優等生だから名前くらいは知っていたかもしれないが、顔を合わせることもほとんどなかったはずだ。
(…この人は一体、私に何を期待してるんだろう)
林田と同様、梓にクールで落ち着いた振る舞いを期待しているのだろうか。
それとも別の何か?
理由を聞けばはっきりすると思った。
が、柊ははぐらかすように、
「内緒」
自分だけの秘密を守るように、不敵に笑った。
「何でそんなこと聞くの?」
そして反撃するように返す。
まさか正直に答えるわけにはいかず、
「べ、別に…」
梓もはぐらかす羽目になった。
(結局、理由は何なんだろう)
昨日は気になって、あまり良く眠れなかった。
柊がなぜ梓を好きになったのか。
考えを巡らせていたら睡眠に集中できなかったのだ。
そのことをひたすら考え続けていたのは、柊の言動が気になって、というよりは、
その理由がわかれば柊に諦めてもらえると思ったからだ。
つまり、梓に好意を抱いた理由―――たとえば、家庭的で可愛く思ったとか―――がわかれば、
梓がその条件を満たしていないことを示すことで柊のことは解決できる、と。
「彼氏に振られたばかりだから恋人を作る気はない」とは言えなかった。
何となく言う気がしなかったのだ。
だが、当たり前だが考えても答えは出なかった。
睡眠時間を削って、目覚めの悪さを倍増させただけだった。
(まあたぶん、“落ち着いていてクールな私”を望んでるんだろうけど)
「じゃ、小テスト始めるぞー」
しかも、まだ完全に眠気の去らない一時間目から、よりによって柊の授業だ。
前の席から回される答案用紙を受け取って、梓はため息をついた。
始め、という声と共にテストが開始された。
「………」
自分でも眉間の皺が増えていくのがわかる。
割と考えさせる問題だ。
なのに眠気が取れなくて集中できない。だから午前中の授業は嫌だ。
柊に、昨日のことが原因で点数が取れなかったなど勘繰られたくない。
梓はいったん椅子に深く腰掛けて、まだ去ってくれない眠気を取り払おうとした。
その時ふと、教壇の柊が目に留まった。
「!」
―――見ている。
こちらをじっと見ている。
柊の目に、梓の姿が映っている。
決して目を逸らそうとしない。
(な…なに!?)
動揺のため頬が紅潮するのを感じて、梓は慌てて顔を伏せた。
こんなことは初めてだ。
告白されたあとも、柊の態度が急に変わるということはなかったのに。
こんなに露骨に梓を凝視するなんてことは、今までなかったことだ。
梓に告白するときでさえ、どこか冗談ぽい響きを持たせていた柊。
だが今の彼の目線は、真剣そのものだった。
(しゅ、集中しなきゃ)
答案用紙に目を走らせる。
けれど目に飛び込んでくる文字は右から左に抜けていき、全く思考に役立たない。
目を合わせなくても柊の視線を感じて、数学どころではなかった。
結局梓は、半分も問題を解くことができなかった。
「―――どういうつもりですか?」
放課後、梓は柊を捕まえて数学準備室へ連れて行った。
人気のないここはこういう時に役に立つ。
梓が自ら彼をここに入れることになるとは、皮肉なものだ。
「何が?」
明らかに苛立っている梓を目の前にしても、柊は動じない。
「とぼけるのはよしてください。どうしてあんな目で見るんですか!? しかも授業中に!」
梓にしてみれば迷惑極まりなかった。
数学の授業のたびにあんなふうに凝視されたらたまらない。
「好きな女を見て何が悪いんだ?」
「!!」
真剣な瞳だった。
梓がたじろぐほどの。
「悪いけど、櫻井が迷惑だろうと引く気はないよ。どんな手を使ってもこっちを向かせて見せる。
絶対に逃がさない」
柊の手が、ゆっくりと梓のほうへ伸びてくる。
骨ばった指が彼女の頬へ触れる直前、梓は弾かれたように駆け出した。
一度も振り返ることなく。
下駄箱までたどり着いてようやく足を止めたときには、心臓は手が付けられないほど跳ねていた。
それから数日、梓は柊を徹底的に避けた。
数学の授業中は一度も目を合わせないようにしたし、頻繁になされる呼び出しにも一切応じなかった。
相手は「作戦」を変更してきたのだ。
ならばこちらも対応を変えなくては。
(最初からこうすればよかったのよ、最初から……)
彼の視線に肌がちりちりと焼けつくようになるのは錯覚。
動悸が早くなるのも偶然だ。
気にしなければ、いずれ収まる。
もう恋をして傷つくのは嫌だった。努力をしたって無駄なのだ。
今度もそうならないとどうして言える?
「ごめん梓、あたし教室に忘れ物しちゃった。先行ってて」
結衣はそう言って、もと来た廊下を小走りで駆けていった。
二人は物理室へ行く途中だった。仕方なく梓は一人で教室に向かう。
一人になると自然とため息が漏れた。
(…やっぱり私、まだ吹っ切れてないのかな)
彼氏に振られてから泣き暮らすということはなかったものの、何となくあの日から気分は浮上できず沈んだままだ。
だから新しい恋に行こうという気にならないのかもしれない。
努めて冷静に別れ話に応じたものの、心のどこかでは納得できない部分があったということだろうか。
「梓?」
下を向いて歩いていた梓は、前から近づいてくる人影に気付かなかった。
名を呼ばれて初めて気付いた。
「林田…くん」
林田修二だ。
梓の心臓はどくんと跳ねた。
表情が凍りつく。
だが彼女の内心は、ほとんど表に反映されない。
彼女の反応しだいでは林田も声をかけるのをためらったろうが、
顔を上げた彼女を見て林田は、彼らしい悪気のない無神経さで話しかけた。
「久しぶり…元気そうじゃん」
(…元気?)
元気なわけない。
ここのところ不安定になっていた心が、ここに来て一気にきしみ始めた。
「…うん」
なのに言葉は正反対のことを言う。
自分でない誰かが勝手にしゃべっているようだ。
せっかく最近顔を合わせずに済んでいたのに。
どうして彼の存在に気付かなかったんだろう。
気付いていれば避けられた。
会いたくなんてなかった。
ただでさえ柊のことで、林田とのことを思い出すことが多くなっていたというのに。
感情が決壊寸前まであふれ出す。
立っているのさえ困難になってきた。
林田が何か話しているようだが、何も耳に入ってこない。
代わりに聞こえてきたのは、厳しく鋭い声だった。
「こら、そこの二人。もう授業始まるぞ」
柊だった。
授業に行く途中だったのだろうか、手に数学の教科書を持っている。
柊に指摘されて初めて、休み時間が終わりに近づいていることを知ったようで、林田はあわてて教室へ戻っていった。
廊下には柊と梓だけが残された。
「…大丈夫か?」
目を逸らしつつもはい、と返事をしようとしたところで、梓の頭に恐ろしい考えが浮かんだ。
(この人は―――知ってる!?)
思わず顔を上げると、そこに梓を気遣うような柊の瞳があった。
そこで確信した。
大丈夫か?―――これは別れたばかりの恋人と鉢合わせた梓を心配してかけられた言葉だ。
そうに違いない。
(もう…何が何だか分からないよ…!)
なぜ柊が梓のプライベートなことを知っているのか。
恋人と別れたばかりだと知っていてなぜ執拗にアプローチするのか。
傷心の女は自分になびきやすいと思ったのか。
色んな考えが浮かんでは消え浮かんでは消え、もはや冷静な判断などできなかった。
「櫻井?」
柊はそっと梓の肩に触れようとした。
だが梓は後ずさってそれを避ける。
「もう…もう私にかまわないでください」
感情の渦がぐるぐると渦巻いている。
その刹那の梓の心は複雑に入り乱れていたが、その時芽生えた感情は羞恥に似ていた。
「先生はどうせ“クール”な私を期待してるんでしょうけど…私、そんなのに応えられないし、
応えたくないんです! もういっぱいいっぱいで……限界なんです。
二度と私に関わらないでください…!」
柊の横をすり抜け、一目散に駆け出す。
「櫻井!!」
背後から梓を呼ぶ柊の声が聞こえてきたが、彼女は立ち止まらなかった。
涙が出てきた。
なぜ泣いているのか、梓は自分でもわからなかった。
ただ、混沌として収束のつかない感情が、心の中に在った。
次の日学校に向かう梓の足取りは、いつも以上に重かった。
登校時間はいつもなかなかとれない眠気に困らされているけれど、今日はそれすらも気にならないほどだ。
それは言うまでもなく柊が原因である。
彼が担任になったばかりでこのようなことになってしまい、
残りの約一年間を気まずい雰囲気を残したまま過ごすことになると思うと、気が重かった。
だが、朝のHRのため教室に現れたのは、柊ではなく副担任だった。
「柊先生は風邪のためお休みです」
クラスに残念そうな声が満ちた。
クラスメートのその反応を見て、梓は彼が人望ある人気の教師であることを思い出した。
不謹慎だとは思ったが、梓は胸を撫で下ろした。
風邪など二、三日もすれば治ってしまうだろうが、柊と顔を合わせる回数は少ないほうがいい。
梓がそうやって拒絶し続ければ、向こうもいずれ諦めるだろう。
「…じゃあやっぱり、柊先生とは付き合わないのね?」
昨日のいきさつを聞いた結衣は、確認するように尋ねた。
場所はまたも屋上である。
もちろん人がいないことは事前に確かめてある。
「…うん」
昨日は八つ当たりに近い形で感情をぶつけてしまったが、あれはかえって良かったかもしれない。
あそこまで言われて腹の立たない人間などいないだろう。
「まあ、梓が決めたんならもう何も言わないけど……」
そう言いつつも結衣はどこか納得のいかない様子だった。
彼女はたとえ今の恋人に振られたとしてもすぐにもっといい男を見つけようとする。
要するに恋愛についてのバイタリティの違いだろう。
「でもそこまで嫌がるってことは、それだけ先生のことが嫌いなんだね」
「………」
嫌い。
柊が。
そう改めて言われると、よく分からない。
けれどおそらく、柊以上のいい男が現れたとしても、梓は断っていただろう。
たぶんそれは、相手の好悪とは関係のないことなのだ。
それを考えると柊の真摯な気持ちを裏切っているようで気が咎めないでもなかった。
しかしかといって一歩踏み出す勇気は湧かない。
『好きな女を見て何が悪いんだ?』
梓は頭に浮かぶ柊の像を振り払うように首を振った。
もう関係ない。関係ないんだ。
(……雨だ)
帰り道を歩いていると、ぱらぱらと雨粒が頬を打ち始めた。
梓はすばやく鞄の中から折り畳み傘を取り出す。
水色の傘を開いて数分すると、雨は本降りになった。
それから十五分ほど歩いていき、梓は自分の家のある通りへ曲がる。
と、その曲がり角のところに見慣れない車が止まっているのに気づいた。
梓の家が建っている通りは道が狭くなっているため、路上駐車は禁止されている。
そのため、このあたりを訪れる人々はこの角のところに駐車するのが常だった。
この車もどうせそういった人のものだろう、と梓は大して気にも留めなかった。
だが家の前まで来ると、その車の持ち主が誰か瞬時にわかってしまった。
「先生……」
雨に打たれながら柊がこちらを見る。
目は熱で潤み、顔色は青白い。
梓は思わず駆け寄った。
「何考えてるんですか! 風邪引いてるんでしょ!?」
あわてて差していた傘を差し出す。
小さな傘は二人を雨から守るには不十分で、梓の肩や髪はみるみる濡れていった。
柊の息遣いは乱れている。
病人の身で、いったいどれくらいここに立っていたのだろう。
梓はすっかり動揺してしまった。
(どうしてここまでするの?)
柊はしっとり濡れた体をカタカタと震わせている。
けれど梓の手前、その様子を極力彼女に見せないようにしているように思えた。
「…のは…」
「え?」
「いっぱいいっぱいなのは俺も同じだ、櫻井。
お前に避けられただけで―――このザマだよ」
苦しそうな瞳だった。
それは熱のせいだけではない。
途端、罪悪感が胸を焦がした。
あんな扱いをされて、彼が傷つかないはずがない。
冷たく去っていかれる悲しみは、梓が一番よく知っていたはずなのに。
そんなことに、今初めて気付いた。
自分が傷つかないようにすることばかり考えていた自分が恥ずかしい。
柊は立っているのも苦しいらしく、低く呻いて梓の肩に頭を預けた。
「俺はお前に“クール”でいることなんか望んでない。ただ…
俺のために笑って、怒って、そして―――泣いてくれ」
柊が梓を初めて見たのは、学校の裏庭だった。
彼の高校は全面的な禁煙を規則としているため、職員室でも煙草を吸うことができない。
そのため柊は、人気のない裏庭でこっそりと人目を忍んで煙草を吸っていた。
こんなところに来るのは自分だけだと思っていたが、
その時はいきなり複数の人間の声が聞こえたものだから、ずいぶんと焦った。
見回りに来た同僚かと思ったが、違った。生徒が二人。
男のほうは見覚えがなかったが、女のほうは知っていた。
「櫻井梓」。
学年トップ常連の優等生だ。
話したことはなかったが、顔だけは知っている。
(何だ?)
柊はライターの火をつけかけた煙草を慌てて仕舞った。
そして息を潜めてじっとする。
この場を去ってしまいたいところだが、音を立ててしまい彼らに気付かれることのほうを恐れたのだ。
「よく考えたんだけどさ…やっぱり俺ら、別れたほうがいいと思うんだ」
男子生徒の声が聞こえる。
よりによって別れ話かよ、と柊はため息をつきたくなった。
成り行きとはいえ、こういう話を聞くのは気が進まない。
「梓は、俺がいなくても平気だろ?」
(……おいおい)
男子生徒のほうは気まずそうにしながらも、平然とそんなことを言った。
それにも驚いたが、櫻井梓の言葉を聞いて更に驚く。
「―――わかった、別れましょう」
柊には彼女の表情は見えなかったが、声を聞く限り彼女が取り乱しているような感じはなかった。
彼は首をかしげる。
彼らがどのくらい付き合っていたのかは知らないが、普通別れ話を切り出されたら
多少なりとも「別れない」と抵抗するものではないのか。
愛情のある相手ならなおさら。
櫻井梓は、彼のことを大して好きではなかったのだろうか。
だから大して取り乱しもせずに別れを承諾できたのか。
やがて男のほうは、少しためらうようにしつつも裏庭から去っていった。
櫻井梓のほうはまだその場から動こうとしない。
困ったな、と思いつつ柊は少し身を乗り出した。
早く行ってくれないか―――そう思って梓を見ると、柊は彼女の表情に目を見開いた。
―――涙。
彼女の白い頬には、一筋の涙が流れていた。
瞳は凛と前を見据えたまま、それでも堪えきれなかった感情が、結晶のようになって。
その時気付かされた。
彼女が恋人を愛していなかったはずがない。
傷ついていないはずがない。
どうしてそんな簡単なことに気付かなかったのだろう。
柊は彼女が立ち去るまで、魅入られたようにその綺麗な横顔から目が離せなかった。
その時思った。
俺なら泣かせないのに。
あの涙が、俺に向けられたものだったらいいのに―――。
「…一目ぼれと変わらなかったから、軽く見られるのが嫌で…言えなかったんだよ」
梓の肩口に柊の息がかかる。
柔らかな温みに、梓の目から自然と涙が零れた。
柊の両手は背に回り、弱々しい力で彼女を抱きしめ始める。
「櫻井…俺に“あいつ”を重ねて、俺を拒まないでくれ」
「先……」
「俺はお前に出会って初めて、モラルも倫理もどうでもいいと思えた。
お前も“そこ”から一歩前に踏み出して欲しい。その上で―――返事をくれ」
涙で視界がぼやける。
人前で泣くなど、一体何年ぶりだろうか。
「私……私は………」
柊の腕に力がこもった。
耳障りなけたたましい目覚ましのベルで、梓は急に夢の世界から引きずり出された。
だるい体に鞭打って、目覚ましを止める。
いつもの梓はそこでまた眠りの世界へ旅立つところだが、今日はそうしようとした矢先に携帯にメールが入った。
軽快なそのメロディーを聴いた途端、梓はがばりと跳ね起きる。
そして携帯電話を開き、メールを見た。
『おはよう』
予想したとおり、柊からだった。
自然と笑顔がこぼれる。
梓はベッドから出た。
今日からの朝は特別なものになる。
梓と柊は共に前へ進み始めた。
きっとこれから、朝が来るたびに違った自分になれるのだろう。
―――君のことを想って。
fin.
|
